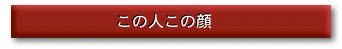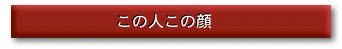川崎市ふれあい館が今年六月に開設十周年を迎える。同館は「だれもが力いっぱい生きていくために」をスローガンに、同胞には民族との出会いを、地域の日本人には異文化に触れる「場」を提供してきた。
川崎市ふれあい館が今年六月に開設十周年を迎える。同館は「だれもが力いっぱい生きていくために」をスローガンに、同胞には民族との出会いを、地域の日本人には異文化に触れる「場」を提供してきた。
チャンゴなどを学ぶ民族文化クラブ、同胞オリニが集まるケナリクラブ、高齢者の交流を図るトラジの会をはじめ、識字学級や成人学級などの学習講座、障害児のための学齢児活動も行っている。日々の実践を積み重ねて10年。さらなる飛躍を期す在日同胞2世のハイ重度館長(54)に話を聞いた。
川崎市南部の桜本商店街。入り口にある韓国乾物店のショーケースの中には、ごく自然に豚足が置いてある。横目に見ながら、ふれあい館に着いたのは平日の夕方だった。
所狭しと駆け回る子どもたちの歓声が、すでに取材を受けていた裵(ペ)館長の声をかき消してしまう。授業を終えた学童保育の子どもたちを中心に、150人くらいの小・中学生が出たり入ったりするから、騒がしいのは当たり前。10年前と変わらない光景が広がる。
子どもたちの4割は同胞オリニで、6割が日本の子どもたちだという。じゃれ合う姿からは、国籍や民族の壁を感じることはない。慣れない手つきでお茶を運んでくれた障害を持つ男の子は、「だれもが力いっぱい生きていく」というスローガンそのままに、きらきらとした目で迎え入れてくれた。
「光陰矢の如し。一生懸命走ってきた」と10年の歩みを振り返る裵館長は、民族伝統のプンムルノリ(農楽)が、地域の祭りで披露できるようになったと喜ぶ。近隣の学校とも「親類づきあい」ができるようになり、在日同胞の問題が「ふれあい教育」や「人権尊重」の一環として授業の中で触れられている。
運動会では桜本保育園の子どもたちも一緒になって農楽を発表する。在日同胞が地域で住民としてようやく受け入れられるようになったのも、ふれあい館の取り組みによるものだ。
しかし、行政が設置し、民間が運営する全国唯一の「公設民営」施設として開設されたふれあい館は、在日同胞に限定されたものではない。広く地域の人たちに門を開いている。
最近の荒れた子どもたちに心を痛める裵館長は、「共通しているのは、家庭にも学校にも地域にも自分の居場所がないことだ」と指摘。老若男女、健常者も障害者も受け入れるふれあい館には、川崎市の「アフター・スクール・チルドレン・ランド」政策で、カバンを持ったまま子どもたちがやって来る。
「ふれあい館に行けば、いろんな楽しい出会いがある」と認知されている証拠である。在日同胞のオリニが同胞の仲間づくりをする場が、週1回の「ケナリクラブ」。日本人の目を気にすることなく、リラックスできる場は、オリニにとって帰る場所、頼れる場所だ。
「同じことを繰り返してきた10年だったが、かつては想像もできなかった民族的な表現が地域に受け入れられるように、変化を生み出している。持続していくことが大事」と裵館長。職員は非常勤を含めて十人。民族講師の派遣などで人手が足りないのが現状だが、ふれあい館に関わった高校生ボランティアたちが不足分を補う。
「高齢化する在日同胞と障害者の受け皿として、第二のふれあい館が必要だ」と新たなスタートを前に意気込んでいる。
(1998.6.3 民団新聞)
|