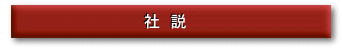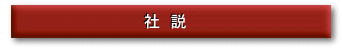「この経験、先生や友達との絆は一生消えない」―。生まれてこの方、どうして私は日本に生まれてしまったんだろう、としか思えず、一人の友人もいないと嘆く在日同胞高校生が勇気を出して昨年の母国夏季学校に参加した。長い人生の中のたった九泊十日間の体験で高校生が得たものは、今後の人生を左右するほど衝撃的だったと、事後の感想文につづっている。
1万5千人の青少年が参加
同胞子弟を対象にした母国夏季学校は一九六六年に開始された。当時、訪韓するチャンスも少なく、韓国に対する誤った情報が氾濫する中で、在日同胞青少年たちはアイデンティティを確立できず、ともすればニヒリズムに陥りがちで、日本社会に埋没していく例も後を絶たなかった。
このような青少年たちを勇気づけ、民族的素養や知識を育む登竜門が必要であると感じた民団が、本国政府に要望して夏季学校が開設された。七九年からは夏に中・高校生、春に大学生と運営方法を変えはしたが、その趣旨は変わらない。すでに一万五千人以上の青少年が祖国を訪れた。
在日同胞社会の基礎学ぶ
いったい祖国とは何なんだろう、自分は何者なのだろう。それを自問自答し、回答を見つけ、そして今後の生き方を模索していく。このような作業の積み重ねが在日同胞社会を構成していく基礎ではないだろうか。その基礎へのアプローチが夏季学校だとはいえまいか。
「韓国人なのに韓国語を全く話せず、歴史・文化も知らない自分が恥ずかしい」と国籍・民族と現実社会のギャップにあえいでいる同胞青年は多い。参加した青年の多くは何らかの答を見つけるだろう。母国修学の門を叩いた者も少なくない。
共通項持つ同世代の友人と交流
一方、自己を見つめるきっかけになると同時にもう一つの大きな側面がある。同じ時代の苦悩や葛藤など数多くの共通項を持つ同世代の友人をつくれることだ。夏季学校に参加した青少年たちが、帰日後もつながりを大切にしてきた。今まで在日であることを明かしてつき合える友達がいなかったある参加者は「同じ在日韓国人の友達ができた」ことが一番の宝物だという。
日本の学校に通う多くの在日同胞生徒が抱える思いであろうことは想像に難くない。
六六年に参加した青年はすでに五十歳を越え、同胞社会の中核を担う世代として育っている。それらの人々が組織であれ、市井の社会であれ、夏季学校で培った“自己発見”を礎に、日本社会の中に埋没せず、社会や家庭で自己の果たすべき役割を果たしている。
下関から船に乗って釜山に着き、朝日に浮かぶ釜山港の姿を見た世代は、「ここがアボジが国を後にした港」「初めての祖国」、思いはさまざまあれど、感慨深い涙を流したはずだ。今は飛行機で玄界灘を越すが、解散を前にして男女の区別なくみなが涙する。
この涙は何を表しているのか。別れを惜しむ涙もあろう。しかし、ただの惜別ではなく、在日同胞という共通項で結ばれた固い絆から生まれる涙だと確信する。
最後に一つの感想文を紹介する。「どんなことがあっても母国夏季学校を続けて欲しい。私みたいに在日の友達がいなかったり、韓国人というプライドをあまり持っていなかった人が、変われる場として」。
引き続き多くの子弟を参加させてほしいと、同胞父母に切に呼びかけたい。
(1998.6.3 民団新聞)
|