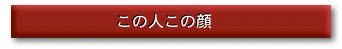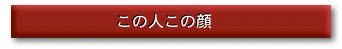アングラ演劇集団新宿梁山泊を率いる在日韓国人二世の演出家、金守珍さんがオーストラリア国立舞台芸術学院(NIDA)での演劇指導を終えて、このほど帰日した。四カ月の滞在期間中、同学院演技コースで学ぶ二年生と共に梁山泊のオリジナル「少女都市からの呼び声」(英訳=A cry from the city of virgins)を一緒に作り上げた。本公演も好評で、会場となったNIDA内パレード・シアターは三百五十席が連日満席となった。金さんにオーストラリアでの体験を聞いた。
アングラ演劇集団新宿梁山泊を率いる在日韓国人二世の演出家、金守珍さんがオーストラリア国立舞台芸術学院(NIDA)での演劇指導を終えて、このほど帰日した。四カ月の滞在期間中、同学院演技コースで学ぶ二年生と共に梁山泊のオリジナル「少女都市からの呼び声」(英訳=A cry from the city of virgins)を一緒に作り上げた。本公演も好評で、会場となったNIDA内パレード・シアターは三百五十席が連日満席となった。金さんにオーストラリアでの体験を聞いた。
芝居の途中で拍手喝采が起きた。口笛が吹き鳴らされ、足で拍子をとる客までいた。新宿梁山泊が日本で公演したときそのままの光景が繰りひろげられるのを目のあたりにした現地の関係者は「ありえないこと」と驚いた。オーストラリアでもカーテンコール時に限って特定の出演者に限って称賛の拍手を贈る−それがごく普通なのだという。
ここは通称NIDA(ナイダ)と呼ばれるオーストラリア最高峰の国立演劇学校。NIDAには三つの本格的劇場がある。その一つ、パレード・シアターでアングラ演劇集団、新宿梁山泊の代表作の一つ「少女都市からの呼び声」(唐十郎作)が上演された。
演じたのは将来芸能界入りを目指して同校演技コースで学ぶ二年生の二十五人。四月二十九日から五月七日まで連日繰り広げられた十ステージは、全三百五十席とも空席を探すのが困難なほどの盛況が続いた。
最終公演が終わると、役者ばかりかスタッフの間からも名残惜しむ声が相次いだ。普通ならば一仕事終えたという解放感に包まれるところ。金さんは「アジアの演劇が受け入られた。“わび”“さび”といった情の世界が共有できた」と喜んでいる。
「ぜひ,NADAの学生公演の演出を」要請したのは、新宿梁山泊の芝居を東京で見て感銘を受けたジョン・クラーク校長だった。もう四、五年前のことだ。劇団の代表としての立場から、四カ月間も日本を留守にできない事情があった。それでも、新たな創造へのエネルギーにしたいとの気持ちから引き受け、二月一日に日本を発った。
招待演出家として選んだ作品「少女都市からの呼び声」は役者時代の八四年、唐十郎さんからプレゼントされたもの。八七年に梁山泊を旗揚げしてからも、演出を変えながら繰り返し上演してきている。九三年には日本文化庁から芸術祭賞も受賞している。
作品としては難解だ。自らは「生まれ出ることのなかったある男の双子の妹が、男の親友を恋する物語をベースに、現実と幻想、シリアスとコミカルの境界を取り去り、高度の視覚効果を多用した情緒に訴えるハイブリッドな作品」と説明している。
果たして文化的背景の異なるオーストラリアで理解されるのか。不安があったようだが、「最終的には望んでいる方向にいった」という。
公演の日、韓国の笛の音が流れるなか、静かに幕があがった。多彩な効果音に乗ってスピーディーに転換する場面。英語で機関銃のごとく放たれるセリフの数々。歌や音楽も随所で使われた。ミュージカルであり、セリフ劇ともいえる梁山泊独特の世界が展開されていく。伝統的形式主義には縛られない舞台は「西洋的スタイルと日本の伝統的スタイルの狭間に位置するといっていいでしょう」と語る。
こうした演出スタイルは韓国・北韓と日本の狭間を生きる在日韓国人としての金さんの生きざまが色濃く反映されている。
大学卒業までは「祖国のために」を第一義に考えて生きてきた。これは都内の朝鮮学校在学中、級友たちが次々に帰国していったことと無縁ではない。自身、東海大で電子工学を学んだのも、帰国を念頭においていたからだった。しかし、父親から引き止められた。
就職の厚い壁にぶつかり、「自分探しの旅」を始める。たまたま、金芝河の芝居「鎮悪鬼(チノギ)」を見たことから芝居の世界に。演劇を通して「自分がどこに存在しているのか。どこから来てどこに行こうとしているのかを考えている」のだという。
その答えはまだみつかってない。逆にそのことがエネルギーの源になっているのかもしれない。来年以降、オーストラリアで作りあげた舞台を俳優ともども日本に持ち込み、上演したいと計画している。
(1998.6.24 民団新聞)
|