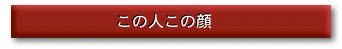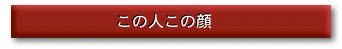「直木賞」にもノミネート
自らの父をモデルにして在日同胞一世の破天荒な生きざまを描いた小説『血と骨』で「山本周五郎賞」を受賞、さらには「直木賞」候補作にもノミネートされた。梁石日さん(61)が一年半振りに書き下ろした新作『血と骨』に対してある在日同胞作家は、ギリシャ悲劇を思い起させると評価した。在日同胞社会での父と子の葛藤を描いた作品は珍しくないが、これほどまで深く描き出した小説はかつてなかったという。在日同胞文学の新地平を切り開いたといってもいいだろう。梁さんに作品の背景などを聞いた。
既存の枠組み超えて
大阪の在日同胞集住地区、旧猪飼野の蒲鉾工場が舞台。一人の業深き人間の激烈な死闘と数奇な運命を、家族や周囲の目線で描く。主人公、金俊平の内面世界にはあえて触れなかったことでそのおどろおどろしさを際立たせた。
体重百キロを超す巨漢、その凶暴ぶりはやくざさえ震え上がらせるほど。酒と博打にのめりこみ、やりばのないうっくつした心情を家族にぶつけるとほうもない存在だ。一家の主人でありながら、もとより生活など顧みようともしない。周囲は翻弄され、ついにはその家族から手痛いしっぺがえしを受ける―。
この金俊平の生きざまは在日同胞一世の典型ともいえよう。梁さん自身「親父がいなかったらこういう小説は書けなかった」という。その実像は作品中にかなり生かされている。
「実際、蒲鉾工場をやっていた。戦前は小さいから人から聞いたことやオモニから聞いたことがないまぜになっている。戦後は僕が見ていたそのとうり」「親父であって、親父ではない存在。恐怖の対象ですよ。憎しみがどんどん蓄積されていきますからね」。
小説としては格好のモデルだが、「親子関係、家族関係で書こうとするとだめだったんですね。憎しみが先行してしまって。そこから離れて、もっと大きな枠組みのなかで考えないと金俊平という主人公は書けなかった」。
梁さんが金俊平を“父親だが父親ではない存在”としてとらえなおしてみたところ、不思議に筆が進みだした。
「彼は人間の欲望とか暴力とか丸裸の状態。いわば人間の原初的な存在なんです。そのうえにいろんなものを着ていった。それをはぎとって“身体性”というものを考える必要があった」。
梁さんにとっての“身体性”とは人間の美点も欠点も兼ね備えた本来の姿。そうしたものが近代化の進展とともに奪われ、いまにいたっては身体が空洞化してしまったというのだ。ここには歴史というものに翻弄されていく「在日」の運命に対する悲しみと怒りが込められている。
梁さんは「『在日』の痛み、置かれている状況は、本国の国民には分からないし、分かる必要もない。だったら自分たちで積極的に『在日』を生きるために、『在日』は『在日』に投資するべきだ」という。一例として、文化活動を支援する基金制度の創設を強く訴えている。
梁さんは一九三六年の大阪生まれ。工員や店員を経て印刷会社を興すも失敗、約二億円の負債を抱えて逃げるようにして大阪をあとにした。当時、二十九歳だった。各地を転々とした後、東京でタクシー運転手をした。この時の体験をもとに四十五歳で作家としてデビュー、なかでも『タクシー狂騒曲』は「月はどっちに出ている」として映画化され各映画賞を総なめにした。『血と骨』は月刊雑誌に十回にわたり連載していた作品をもとに五カ月かけ全面的に書き下ろしたもの。
次回作は「終わりなき始まり」
次回作はすでにある写真誌で昨年末から連載が始まっている『終わりなき始まり』。在日同胞社会の今日的な様々な問題をテーマに描く。
「アイデンティティーに悩んでいる『在日』は多い。一歩踏み出していかないとタコ壷に引き込まれる。枠をはみ出さないと」。梁さんの力強いメッセージがまた聞けそうだ。
(1998.7.29 民団新聞)
|