 | | 火計り焼 |
有田焼で有名な李三平が一五九八年に渡来して、白磁の原料を発見するのに十八年かかった。鹿児島といえば、すぐに連想されるのは桜島の火山灰が積もったシラスで、薩摩の陶工たちがこの地から原料を探し出すのに二十二年、ほぼ一世代かかっている。
壽官陶苑の収蔵庫に展示されている名器「火計り焼」は、韓国のサバル(飯碗)の形をしており、茶道の約束事を無視した初代の沈当吉の作である。火計り焼の由来は、祖国を離れる際に携えてきた薩かな土と釉薬(うわぐすり)を用い、火だけを日本で借りて作ったという意である。
この十月には「薩摩陶工四百年祭」の行事の一環として、全羅北道南原市にある蛟龍山で、古式にのっとって採火が行われる。採火は萬人義塚、オノリラの塔、廣寒楼を一巡して、多くの韓国の若者に守られながら韓国海洋大学のハンナラ号で十九日に鹿児島の串木野に運ばれる。
薩摩焼が世界的に有名になったのは、江戸末期に薩摩藩が幕府に抵抗して「薩摩琉球國」の名でパリ万博に出品したことが契機になった。薩摩焼はそこで高い評価を受けた。豊臣秀吉の韓国侵略で連行された苗代川陶工らが、薩摩の名声を高めたのは、皮肉な運命といえよう。
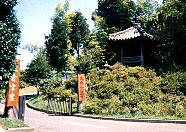 | | 韓国の宮大工を呼び寄せて建てた六角亭 |
一八七三(明治六)年に開かれたオーストリア万博でも薩摩焼きは世界一という大きな評価を受け、大評判となった。その当時の薩摩焼きの主役は、藩窯の主取りであった十二代・沈壽官であった。
現在に残る沈家の格式高い家屋から見ても、当時の評価が推測される。
数年前、久しぶりに壽官家を訪ねた際、韓国の宮大工を呼び寄せて建てたという六角亭に案内された。十四代・沈壽官氏は「琉球王宮の首里城を再建した時に用いられたシロアリ防腐処理をこれにも使ったから、二、三代は保つだろう」と語ってくれた。
韓国の名誉総領事としての資質は、二千五百坪の邸内の方々で確かめられる。
この六角亭も、弁当を持った家族連れがピクニックに訪れるという。故司馬遼太郎氏の『故郷忘じ難く候』に出てくる庭園の臥龍梅(がりゅうばい)は台風の影響を受けて昔の面影を失っていた。
 | | 沈家の庭ではためく韓日両国の国旗 |
沈家歴代の名品を陳列してある「収蔵庫」の看板も司馬氏が揮毫したもので、近日中に全国を巡回する司馬遼太郎作品展に貸し出されるとのことであった。
特筆されるのは、沈家の門を一歩入った所にある韓日両国旗を掲げる二本のポールである。七、八年も前に、門でたまたま出会った韓国から来たという老僧が「日本の果ての鹿児島の山中で太極旗に出会うとは奇遇だ」と感嘆していたことが忘れられない。
百聞は一見に如かず。薩摩焼き四百年祭に、在日のわれわれが直接に接すれば、必ずや肌で民族が何たるかを感ずるであろう。
(1998.10.7 民団新聞)
| 






