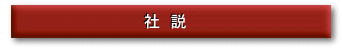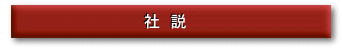日本を代表する焼物、薩摩焼が誕生して今年で四百年を迎えた。薩摩焼は豊臣秀吉が引き起こした壬辰倭乱(文禄・慶長の役)の際に、鹿児島の島津藩によって日本に連行された同胞の陶工たちが興したものだ。
十月十九日には、先祖が捕らえられた韓国全羅北道・南原市の蚊竜山山城で採火式が行われ、陶工の子孫である薩摩焼宗家第十四代の沈壽官氏に「窯の火」が手渡された。土と釉薬は日本に持ってきたが、火だけは持ち込めなかった初代の遺志を引き継ぎ、日本に運ぶためである。こうして四百年目にして初めて故郷の火が海を渡り、かつて苗代川(のしろこ)と呼ばれた美山の地で新しい歴史の一ページを重ねた。
一口に四百年と言うが、異郷の地で風雪に耐えながらしっかりと伝統の技を守り抜いてきた事実に驚嘆するほかない。陶工たちの数奇な運命と今を生きる第十四代については、司馬遼太郎の著書『故郷忘じがたく候』に詳しいが、韓(から)の国に自身の血脈を感じていた司馬氏は、「この村の人にはハートが二つある。一つは韓国に向かって今でも慕情を伝え、今一つは住んでいる地域で立派な人間として生きようとする」と語ったという。
他郷で開花した異文化
第十四代は昨年末、「侵略という極めて不愉快な事実によって初代は渡日を余儀なくされたが、薩摩焼という日本にない文化を定着させた。生産量こそ少ないが、品格、品質とも日本の中で一流のものとして光沢を放つ」と胸中を披瀝した。氏の言葉を待つまでもなく、薩摩焼は一八六七年のパリ万国博や一八七三年のオーストリア万国博で世界の人々から絶賛され、日本の焼物の代名詞として今日にいたっている。
歴史に「たら」「れば」は意味がないが、十四代へと代を継ぐ過程で一人でも伝統に反旗を翻していたら、今日の薩摩焼はなかっただろう。先祖代々が心血を注いだ焼物という民族の文化に幼い頃から浸かってきた環境とそれを受け入れた各時代の陶工の感性が溶け合い、今日の結実がある。
未来へ続く韓日の太い絆を
第十四代が四百年祭にかけた思いは、故郷の火を日帝三十六年を経験していない韓国と日本と在日の若い手で日本に運び、その火を燃やして四百一年目の輝かしい韓日の歴史の始まりを告げたい、というものであった。ぎくしゃくした過去に訣別し、未来を志向する新しい韓日関係は、金大中大統領の訪日メッセージとも重なる。
金大統領は韓日の友好関係を築く上で、文化交流の大切さを説き、日本の大衆文化を段階的に開放することを明らかにした。すでにその作業が始まったと外電は伝えている。使い古された「近くて遠い国」を一衣帯水の関係にしていくためには、まずは互いの胸襟を開いて接することから始めるのがいい。その役割を果たすのは、韓日交流の架け橋と位置づけられた在日同胞、とりわけ若い世代である。
われわれ在日同胞の歴史は、解放後だけでもすでに半世紀を刻み、日本生まれの二・三世が同胞社会の九割を占めるようになった。本国の同胞とも一世とも異なる「氏より育ち」を地でいく「在日」が同胞社会の中核を成しているが、自らの民族性を否定して日本社会に埋没したり、民族からの逃避行を繰り返していては、架け橋にはなることはできない。
秋の夜長に伝統の火を絶やさなかった薩摩焼に思いを馳せて、守り続ける民族とは何か、韓日交流のために自分に何ができるかを考えてみるのも意味がある。
(1998.10.28 民団新聞)
|