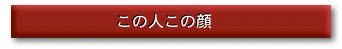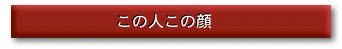■深層に心理に切り込み新境地
「愛を乞うひと」(下田治美原作、角川文庫)で昨年から今年にかけて、日本映画界の各脚本賞をほぼ総なめにした。話題作「月はどっちに出ている」で見せた独特のユーモアと細やかなキャラクター描写が鄭義信さん(41)の持ち味といわれてきたが、今回は一転して人間の深層心理に深く切り込むことで新境地を開拓した。九四年に劇団新宿梁山泊を退団して以来、活動のフィールドを映画界のほか、テレビ・ラジオのシナリオにも広げている鄭さん。各方面から次の活動が期待されている一人だ。
■テレビ・ラジオにも活動拡大
数ある脚本賞の中でもなにより「キネマ旬報脚本賞」の受賞を喜んだという。映画少年のときからの「憧れの賞」だったのだ。崔洋一監督と共同執筆した「月はどっちに出ている」に続いて二度目だが、今回は単独受賞。感激の度合いが違う。
「愛を乞うひと」は幼児虐待をテーマにしている。平山秀幸監督が長年、映画化を夢見てきた作品で、脚本化にあたって鄭義信さんに白羽の矢を立てた。
いたいけな少女に対する八年間にわたる母親、豊子の凄まじい折檻。殴ったり、蹴ったり、時には裸にしてむちを使い叩く。何度も殺されかけるヒロイン、照恵。それでもひたすら母に愛を欲し続けた。成長してからは母への限りない憎しみと愛への渇望のなかでさまよい続けたうえ、身を賭して親子の絆をさがす旅へと向かう。
三十年後、照恵が豊子のもとへ出向く緊迫したラスト。原作では照恵が遠目に豊子の姿を確認するだけで終わっている。これに対して、鄭さんはあえて二人を出会わした。ガラス戸越しに交わされる会話の内容をどうするか、シナリオづくりでは「何度も書き直した」。鄭さんが最も悩んだ部分だ。最終的には八稿にまで及んだ。
鄭さんは、豊子自身、親に同じような虐待を受けていたと想定した。愛された経験がないゆえに自分も人を愛せない"虐待の連鎖"だ。加害者であって一方では被害者でもあったというこうした錯綜した構図を説得力あるものにするため、映画では、原作には出てこない豊子の陰の生き様をつぶさに描写し、過去と現在がオーバーラップしていく手法をとった。この結果、鄭さんの狙いとした"親子の絆"は確かなメッセージとなって観客に伝えられた。
豊子という人間は原作を読む限りでは「ただの狂女」でしかない。しかし、鄭さんはそうはしたくなかったという。脚本化にあたって、平山秀幸監督に「この二人は出会わなければいけない」と提案したのは鄭さんだった。人間に対するこうしたヒューマニズムの眼差しは少年時代に養われたもの
兵庫県姫路市内の在日同胞集落で生まれ育った。家業は廃品回収。周囲を刑務所、病院、火葬場という"三点セット"に囲まれた環境の中、社会の底辺で必死になって生きる人たちを目の当たりにしてきた。
決定的だったのが、廃品回収の本の中から児童小説「クオレの日記」を探し当てて読んだこと。作品は十二歳の少年エンリコの学校生活を、一年間の日記につづったもの。「感銘を受けた」鄭さんは、やがて文学への憧れを抱くようになった。
同志社大学を中退して上京、横浜放送映画専門学校美術科に学ぶ。やがて演劇に転じ、劇団黒テントを経て八六年に劇団新宿梁山泊の旗揚げ公演に参加、座付き作家として一躍脚光を浴びる。「千年の孤独」で雑誌テアトロ賞、「ザ・寺山」では第三十八回岸田國士戯曲賞を受賞している。九一年からは映画界にも脚本家として進出、「月はどっちに出ている」をはじめとした数々の話題作を崔監督と共同で脚本化してきた。
梁山泊時代はアルバイトで生計を立てた。いまはその必要こそ無くなったものの、脚本家としてやっていけるのか不安を消せないできたという。
「愛を乞う人」での数々の受賞は、鄭さんが今後とも職業作家として活躍してゆけるという証明といってもいいだろう。
(1999.04.07 民団新聞)
|